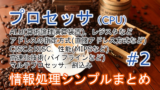このページでは,基本情報技術者試験をはじめとする情報処理技術者試験で必須となる,バスと入出力インタフェースについてシンプルにまとめています。バスについては,伝送方式(パラレル伝送方式・シリアル伝送方式)や,内部バス・外部バス・拡張バスなどの種類を整理しています。また,入出力インタフェースについては,IDE(ATA),SATA,SCSI,USB(規格やコネクタ形状),IEEE1394,IrDA,Bluetoothまで,各装置の特徴を確認できます。用語や規格が多く混乱しやすいですが,全体像を意識しながら読み進めてみてください。
バスとは(コンピュータ内・外部のデータ経路)
バスとは,コンピューターの内部でデータをやり取りするための伝送路のことをいいます。
バスの伝送方式
パラレル伝送方式とは
パラレル伝送方式は,送信するデータのビット数分の信号線を使用して,1クロックで同時に複数のビットを並列に伝送します。16本の信号線を使用した場合は1クロックで16ビット,32本の信号線を使用した場合は1クロックで32ビットのデータを送信できます。
伝送速度を上げるためには,バス幅(1クロックで送信できるデータ量)を広げたり,バスクロックを上げたりします。しかし,バス幅を広げる場合,信号線を増やせばマザーボードの配線が難しくなりますし,また,平行する信号線が干渉し合うという問題も出てきます。バスクロックを上げる方法についても,バスに接続される機器が増えると波形が乱れるという問題があります。よって,今現在,実際には,伝送速度を上げにくくなってきています。
シリアル伝送方式とは
シリアル伝送方式は,データを1本の信号線を使用して1クロックで1ビットずつ伝送します。パラレル伝送方式と比べると,信号線の本数が少ないためケーブルが扱いやすく伝送距離も長いです。そのため,主にコンピューターと外部周辺機器との接続に使用されてきました。
伝送速度を上げる場合,他の信号線と同期をとる必要がないため高速化しやすいです。そのため,最近は,HDDやSSDなど,コンピューター内部の機器との接続にも使われています。
バスの種類
パソコンのマザーボードの場合,次のようなバスが搭載されています。
※ 1つのバスに複数の装置が接続されている場合,複数の装置が同時にデータを送信することはできない
※ バスのデータ転送速度が遅い場合,CPUの性能をフルに発揮することはできない
チップセットとは,CPUや主記憶装置,拡張スロットなどの間でデータ伝送の制御を行う集積回路(ICチップ)のことをいいます。以前は,ノースブリッジとサウスブリッジの間を高速な内部バスで接続する構成が一般的でしたが,最近は,ノースブリッジのほとんどの機能がCPUに統合されています。
ノースブリッジは,CPUや主記憶装置,ビデオカードなどを接続するCPUに近い側の高速なチップです。メモリコントローラハブともいいます。
サウスブリッジは,BIOSやISA,ATA,SATA,PS/2,USB,ネットワークなどを接続するCPUから遠い側の比較的低速なチップです。
それぞれのバスは,次の3つを組み合わせて構成されることが多いです。
データバス
データバスは,指定された場所に格納されている実際のデータを伝送するためのバスである。伝送するデータは,演算に使用する数値や,その演算結果,周辺装置からの入力データや出力データである。
アドレスバス
アドレスバスは,各装置やメモリーの場所を指示する情報を伝送するバスである。データの送受信時には,データの読み出し元や,格納先を指定する必要がある。
コントロールバス
コントロールバスは,アドレスで指定された場所に対して,読み出しをするのか書き込みをするのかなど,各装置を制御する信号を伝送するバスである。
これらのバスについては,「プロセッサの基礎まとめ」も参照してみてください。
内部バスとは
内部バスは,CPU内部の回路間を結ぶバスです。CPU内部の算術論理演算装置(ALU),命令レジスタ,汎用レジスタ,その他のレジスタ,キャッシュメモリなどを結びます。パラレル伝送で,32ビットや64ビットなどがあり,このバス幅がCPUの性能指標として使われています。
外部バスとは
外部バスは,CPUと主記憶装置やチップセットを結ぶバスです。
メモリバスとは
CPUと主記憶装置を結ぶバスです。
フロントサイドバスとは
CPUとチップセットを結ぶバスです。
拡張バスとは
拡張バスは,PCと周辺装置を結ぶバスです。パソコンの機能を拡張するために使用します。PCIや,PCI Expressがあります。
※ PCI Expressは,PCIの後継の接続規格で,ビデオカードの接続方式などとして広く普及している
広告
入出力インタフェースとは(周辺機器接続規格の基礎)
有線方式の入出力インタフェース
IDE(ATA:Advanced Technology Attachment)とは
IDEは,コンピューターにハードディスクを接続するためのパラレルインタフェース規格です。業界標準として普及していました。
ATAは,このIDEを標準化した規格です。ハードディスクやCD-ROMドライブなどのストレージ装置を接続します。現在,ATA規格のハードディスクは生産を終了しています。
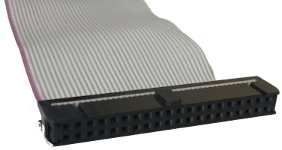
シリアルATA(SATA)とは
シリアルATAは,ATAをシリアルバスにした規格です。ハードディスクやSSD,光学ドライブなどを接続します。ホットプラグに対応しています。

| 規格 | 転送速度 |
|---|---|
| SATA1 | 150Mバイト/秒 |
| SATA2 | 300Mバイト/秒 |
| SATA3 | 600Mバイト/秒 |
ホットプラグとは,コンピューターの電源が入っている状態で,周辺装置を接続して利用できるしくみをいいます。
SCSI(スカジー)とは
SCSIは,ハードディスクや他の周辺装置を接続するパラレルインタフェース規格です。接続する装置に0~7の番号を割り当て数珠つなぎ(デイジーチェーン)にします。最大で7台まで接続できます。現在,SCSIは,あまり使われていません。

※ 汚れたケーブルですみません。一応,洗ってみたんですが…。これしか,なかったんです。
USB(Universal Serial Bus)とは(汎用シリアルバス規格)
USBは,コンピューターにキーボードやマウス,プリンター,各種ドライブなどを接続するためのシリアルインタフェース規格で,現在,広く普及しています。ホットプラグに対応しており,USBハブを使用することで,1台のコンピューターに最大で127台の周辺装置を接続することができます。また,プラグアンドプレイにも対応しています。
※ ホットプラグについては上記参照

プラグアンドプレイとは,コンピューターに周辺装置や拡張カードなどを接続した際に,デバイスドライバのインストールを自動的に行うしくみをいいます。
※ デバイスドライバ(ドライバ)とは,コンピューターに接続した機器を動かすためのソフトウェアのことをいう
USBの規格
| USB1.1 | フルスピード | 12Mビット/秒 |
| USB2.0 | ハイスピード | 480Mビット/秒 |
| USB3.0 | スーパースピード | 5Gビット/秒 |
| USB3.1 | スーパースピードプラス | 10Gビット/秒 |
コネクタの形状
| Type-A | USB2.0 | パソコンや充電器など,電力を供給する側に接続するコネクタ 色は黒,または,白が多い | |
| USB3.0 USB3.1 | パソコンや充電器など,電力を供給する側に接続するコネクタ 色は水色が多い ※ USB2.0 Type-Aと互換性あり | ||
| Type-B | USB2.0 | 周辺装置側のコネクタ スキャナーやプリンター,外付けHDDなどを接続する | |
| USB3.0 USB3.1 | 周辺装置側のコネクタ USB2.0 Type-Bの端子の上部に追加の端子が配置されている 外付けHDDなど,速度重視の装置を接続することが多い ※ USB2.0 Type-Bとは互換性がない | ||
| Type-C | USB3.0 USB3.1 | パソコン側でも,周辺装置側でも接続可能なコネクタ 上下は関係なく接続できる スマートフォンやタブレット,ノートパソコンなどの接続や充電(7.5W)に使用される オルタネートモード(Alternate Mode)対応の場合は,映像信号などUSB規格以外の信号を送信できる PD(USB Power Delivery)対応の場合は,最大で100Wの給電が可能となるので,ノートパソコンの充電もできる ※ 最近は,このType-Cに統一する方向に進んでいる | |
| Mini A | USB2.0 | ほとんど見かけることがない | |
| Mini B | USB2.0 | 周辺装置側のコネクタ ディジタルカメラやゲーム機などを接続する | |
| Micro A | USB2.0 | ほとんど見かけることはない | |
| USB3.0 USB3.1 | ほとんど見かけることはない | ||
| Micro B | USB2.0 | 周辺装置側のコネクタ スマートフォンやタブレットを接続する | |
| USB3.0 USB3.1 | ほとんど見かけることはない |
USBケーブル(コネクタの組み合わせ)
| USB Type-A (パソコンなど) | ⇔ | USB Type-B (プリンター,外付けHDDなど) |
| USB Type-A (パソコンなど) | ⇔ | Mini USB Type-B (ディジタルカメラなど) |
| USB Type-A (パソコンなど) | ⇔ | Micro USB Type-B (タブレットなど) |
| USB Type-A (パソコンなど) | ⇔ | USB Type-C (MacBookなど) |
| USB Type-C (パソコン,モバイルバッテリーなど) | ⇔ | USB Type-C (タブレットなど) |
IEEE1394とは
IEEE1394は,コンピューターに周辺装置やディジタル家電などを接続するためのシリアルインターフェース規格です。電源供給もできます。ホットプラグに対応しており,最大で63台の装置を数珠つなぎ(デイジーチェーン接続)(または,ツリー接続)することができます。また,プラグアンドプレイにも対応しています。伝送速度には,100Mビット/秒,800Mビット/秒,3.2Gビット/秒などがあります。
※ ホットプラグ,プラグアンドプレイについては,上記参照

広告
無線方式の入出力インタフェース
IrDA(Infrared Data Association)とは
IrDAは,赤外線を利用した無線方式の入出力インタフェースです。通信範囲は数十cm~1mと狭く,間に障害物があると通信できません。主に,携帯電話やノートパソコン,ディジタルカメラなどで利用されています。
Bluetoothとは
Bluetoothは,電波を利用した無線方式の入出力インタフェースです。通信範囲は2m~10mくらいです。IrDAよりも通信範囲が広く,高速です。ワイヤレスのマウスやキーボード,ゲーム機のコントローラ,ヘッドホンなど,携帯情報機器やオーディオ機器などで利用されています。
まとめ
今回は,バスと入出力インタフェースについて,全体像を意識しながらシンプル!?にまとめてみました。規格名や用語が多く,最初は少しごちゃごちゃして感じるかもしれませんが,「どこをつなぐのか」「有線か無線か」「高速かどうか」といった視点で整理すると理解しやすくなります。一度で覚えきれなくても問題ありませんので,復習用として繰り返し読み返しながら,少しずつ整理していきましょう。
理解が進んだら,過去問題等にもチャレンジしてみてください。