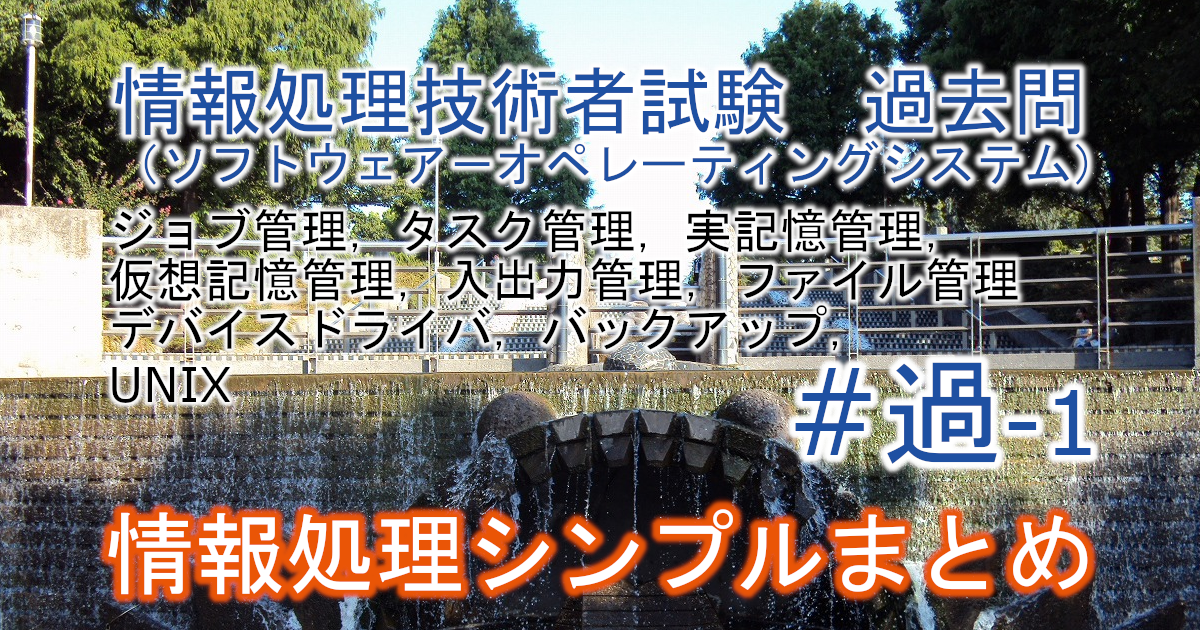このページでは,基本情報技術者試験を中心に,ソフトウェア(オペレーティングシステム)分野の過去問題・サンプル問題・公開問題を掲載しています。ジョブ管理,タスク管理,リアルタイムOS,記憶管理(実記憶・仮想記憶),ファイル管理,デバイスドライバなど,頻出のテーマについて理解度を確認できます。解けなかった問題は,各問題下の【参考】リンクから対応する解説ページを読み,理解した上でもう一度解いてみてください。
平成27年度 基本情報技術者試験 秋期 午前 問16
平成22年度 基本情報技術者試験 春期 午前 問19
問 システム全体のスループットを高めるために,主記憶装置と低速の出力装置とのデータ転送を,高速の補助記憶装置を介して行う方式はどれか。
| ア スプーリング | イ スワッピング |
| ウ ブロッキング | エ ページング |
【解答】ア
【解説】
■ スプーリング
CPUの待ち時間を短くするために,低速な入力装置からの入力データや,出力装置への出力データを一時的に記憶装置に保存し,CPUの処理とは別に並行して(少しずつ転送して)処理するしくみをいう。スループットを向上させることができる。
たとえば,プリンターで印刷する場合,プリンターへの出力データを一時的に磁気ディスク装置に蓄えておき,そこからデータを取り出しながら印刷する(その間,CPUは他の処理を実行する)。
平成27年度 基本情報技術者試験 春期 午前 問17
問 スプーリングの説明として,適切なものはどれか。
ア キーボードからの入力データを主記憶のキューに一旦保存しておく。
イ システムに投入されたジョブの実行順序を,その特性や優先順位に応じて決定する。
ウ 通信データを直接通信相手に送らず,あらかじめ登録しておいた代理に送る。
エ プリンタなどの低速な装置への出力データを一旦高速な磁気ディスクに格納しておき,その後に目的の装置に出力する。
【解答】エ
【解説】
■ スプーリング
CPUの待ち時間を短くするために,低速な入力装置からの入力データや,出力装置への出力データを一時的に記憶装置に保存し,CPUの処理とは別に並行して(少しずつ転送して)処理するしくみをいう。スループットを向上させることができる。
たとえば,プリンターで印刷する場合,プリンターへの出力データを一時的に磁気ディスク装置に蓄えておき,そこからデータを取り出しながら印刷する(その間,CPUは他の処理を実行する)。
ア キュー(先入先出のデータ構造)
イ タスク管理
エ プロキシサーバー
平成30年度 基本情報技術者試験 秋期 午前 問17
平成26年度 基本情報技術者試験 秋期 午前 問18
問 スプーリング機能の説明として,適切なものはどれか。
ア あるタスクを実行しているときに,入出力命令の実行によってCPUが遊休(アイドル)状態になると,他のタスクにCPUを割り当てる。
イ 実行中のプログラムを一時中断して,制御プログラムに制御を移す。
ウ 主記憶装置と低速の入出力装置との間のデータ転送を,補助記憶装置を介して行うことによって,システム全体の処理能力を高める。
エ 多数のバッファから成るバッファプールを用意し,主記憶装置にあるバッファにアクセスする確率を上げることによって,補助記憶装置のアクセス時間を短縮する。
【解答】ウ
【解説】
■ スプーリング
CPUの待ち時間を短くするために,低速な入力装置からの入力データや,出力装置への出力データを一時的に記憶装置に保存し,CPUの処理とは別に並行して(少しずつ転送して)処理するしくみをいう。スループットを向上させることができる。
たとえば,プリンターで印刷する場合,プリンターへの出力データを一時的に磁気ディスク装置に蓄えておき,そこからデータを取り出しながら印刷する(その間,CPUは他の処理を実行する)。
ア マルチタスク
イ 割込み
エ ディスクキャッシュ
平成29年度 基本情報技術者試験 春期 午前 問16
問 四つのジョブA~Dを次の条件で実行し印刷する。全ての印刷が完了するのは,ジョブを起動してから何秒後か。
〔条件〕
(1) ジョブは一斉に起動され,多重度1で実行される。
(2) 優先順位はAが最も高く,B,C,Dの順に低くなる。
(3) 各ジョブの実行後,スプーリング機能が1台のプリンタを用いて逐次印刷を行う。
(4) 各ジョブを単独で実行した場合の実行時間と印刷時間は,表のとおりである。
(5) その他のオーバヘッドは考慮しない。
| ア 100 | イ 160 | ウ 190 | エ 280 |
【解答】ウ
【解説】
各ジョブの進行状況を図にすると,次のようになる。
平成24年度 基本情報技術者試験 春期 午前 問20
問 次の条件で四つのジョブがCPU処理及び印刷を行う場合に,最初のCPU処理を開始してから最後の印刷が終了するまでの時間は何分か。
〔条件〕
(1) 多重度1で実行される。
(2) 各ジョブのCPU処理時間は20分である。
(3) 各ジョブはCPU処理終了時に400Mバイトの印刷データをスプーリングする。スプーリング終了後にOSの印刷機能が働き,プリンタで印刷される。
(4) プリンタは1台であり,印刷速度は100Mバイト当たり10分である。
(5) CPU処理と印刷機能は同時に動作可能で,互いに影響を及ぼさない。
(6) スプーリングに要する時間など,条件に記述されていない時間は無視できる。
| ア 120 | イ 160 | ウ 180 | エ 240 |
【解答】ウ
【解説】
各ジョブの進行状況を図にすると,次のようになる。
平成27年度 基本情報技術者試験 春期 午前 問21
問 出力待ちの印刷要求を,同一機種の3台のプリンタA~CのうちAから順に空いているプリンタに割り当てる(Cの次は再びAに戻る)システムがある。印刷要求の印刷時間が出力待ちの順に,5,12,4,3,10,4(分)である場合,印刷に要した時間が長い順にプリンタを並べたものはどれか。ここで,初期状態ではプリンタは全て空いているものとする。
| ア A,B,C | イ B,A,C | ウ B,C,A | エ C,B,A |
【解答】ア
【解説】
各プリンタの印刷の進行状況を図にすると,次のようになる。
平成31年度 基本情報技術者試験 春期 午前 問16
問 タスクのディスパッチの説明として,適切なものはどれか。
ア 各タスクの実行順序を決定すること
イ 実行可能なタスクに対してプロセッサの使用権を割り当てること
ウ タスクの実行に必要な情報であるコンテキストのこと
エ 一つのプロセッサで複数のタスクを同時に実行しているかのように見せかける機能のこと
【解答】イ
【解説】
■ ディスパッチ
実行可能状態にあるタスクにCPUを割り当てること
平成23年度 基本情報技術者試験 秋期 午前 問20
問 図はマルチタスクで動作するコンピュータにおけるタスクの状態遷移を表したものである。実行状態のタスクが実行可能状態に遷移するのはどの場合か。
ア 自分より優先度の高いタスクが実行可能状態になった。
イ タスクが生成された。
ウ 入出力要求による処理が完了した。
エ 入出力要求を行った。
【解答】ア
【解説】
■ タスクの状態遷移
| ① | 実行可能状態→実行状態 (実行中のタスクが終了したり他の状態に遷移した場合で)CPUを割り当て可能なタスクが実行可能状態の待ち行列にある場合,(そのタスクに)CPUが割り当てられ実行状態に遷移する ※ ディスパッチ…実行可能状態にあるタスクにCPUを割り当てること |
| ② | 実行状態→実行可能状態 CPUに割り当てられた時間(タイムスライス)を使い切った場合や,より優先順位の高いタスクが実行可能状態になりCPUの使用権を奪われた場合に,実行中のタスクは処理を一時中断し,実行可能状態に遷移する ※ プリエンプション…実行中のタスクを一時的に中断すること |
| ③ | 実行状態→待ち状態 割り当てられたタイムスライスを使い切らないうちに入出力要求(SVC割込み)があった場合,待ち状態に遷移する |
| ④ | 待ち状態→実行可能状態 タスクの入出力処理が終了した場合(入出力割込み)に,実行可能状態に遷移する |
令和元年度 基本情報技術者試験 秋期 午前 問18
平成29年度 基本情報技術者試験 秋期 午前 問18
平成25年度 基本情報技術者試験 秋期 午前 問18
問 優先度に基づくプリエンプティブなスケジューリングを行うリアルタイムOSで,二つのタスクA,Bをスケジューリングする。Aの方がBよりも優先度が高い場合にリアルタイムOSが行う動作のうち,適切なものはどれか。
ア Aの実行中にBに起動がかかると,Aを実行可能状態にしてBを実行する。
イ Aの実行中にBに起動がかかると,Aを待ち状態にしてBを実行する。
ウ Bの実行中にAに起動がかかると,Bを実行可能状態にしてAを実行する。
エ Bの実行中にAに起動がかかると,Bを待ち状態にしてAを実行する。
【解答】ウ
【解説】
■ タスクの状態遷移
| ① | 実行可能状態→実行状態 (実行中のタスクが終了したり他の状態に遷移した場合で)CPUを割り当て可能なタスクが実行可能状態の待ち行列にある場合,(そのタスクに)CPUが割り当てられ実行状態に遷移する ※ ディスパッチ…実行可能状態にあるタスクにCPUを割り当てること |
| ② | 実行状態→実行可能状態 CPUに割り当てられた時間(タイムスライス)を使い切った場合や,より優先順位の高いタスクが実行可能状態になりCPUの使用権を奪われた場合に,実行中のタスクは処理を一時中断し,実行可能状態に遷移する ※ プリエンプション…実行中のタスクを一時的に中断すること |
| ③ | 実行状態→待ち状態 割り当てられたタイムスライスを使い切らないうちに入出力要求(SVC割込み)があった場合,待ち状態に遷移する |
| ④ | 待ち状態→実行可能状態 タスクの入出力処理が終了した場合(入出力割込み)に,実行可能状態に遷移する |
平成28年度 基本情報技術者試験 秋期 午前 問18
問 マルチプログラミングにおけるプロセスの切替え手順を示した図において,OSの処理a~cとして,適切な組合せはどれか。
a | b | c | |
| ア | 実行状態の回復 | プロセスの選択 | 実行状態の退避 |
| イ | 実行状態の退避 | 実行状態の回復 | プロセスの選択 |
| ウ | 実行状態の退避 | プロセスの選択 | 実行状態の回復 |
| エ | プロセスの選択 | 実行状態の回復 | 実行状態の退避 |
【解答】ウ
【解説】
■ 割込み
実行中の処理を中断させ,強制的に別の処理を実行させることをいう。
同時に複数の割込みが発生した場合は,優先順位の高いものから実行される。
平成30年度 基本情報技術者試験 秋期 午前 問16
平成25年度 基本情報技術者試験 春期 午前 問18
問 三つのタスクの優先度と,各タスクを単独で実行した場合のCPUと入出力(I/O)装置の動作順序と処理時間は,表のとおりである。優先度方式のタスクスケジューリングを行うOSの下で,三つのタスクが同時に実行可能状態になってから,全てのタスクの実行が終了するまでの,CPUの遊休時間は何ミリ秒か。ここで,CPUは1個であり,1CPUは1コアで構成され,I/Oは競合せず,OSのオーバヘッドは考慮しないものとする。また,表中の( )内の数字は処理時間を示すものとする。
| ア 2 | イ 3 | ウ 4 | エ 5 |
【解答】イ
【解説】
各タスクの進行状況を図にすると,次のようになる。
平成30年度 基本情報技術者試験 春期 午前 問16
問 三つのタスクA~Cの優先度と,各タスクを単独で実行した場合のCPUと入出力(I/O)装置の動作順序と処理時間は,表のとおりである。A~Cが同時に実行可能状態になって3ミリ秒経過後から7ミリ秒間のスケジューリングの状況を表したものはどれか。ここで,I/Oは競合せず,OSのオーバヘッドは考慮しないものとする。また,表中の( )内の数字は処理時間を表すものとし,解答群の中の“待ち”は,タスクが実行可能状態にあり,CPUの割り当て待ちであることを示す。
| ア |
| イ |
| ウ |
| エ |
【解答】ウ
【解説】
各タスクの進行状況を図にすると,次のようになる。
平成26年度 基本情報技術者試験 秋期 午前 問17
平成22年度 基本情報技術者試験 秋期 午前 問20
問 2台のCPUから成るシステムがあり,使用中でないCPUは実行要求があったタスクに割り当てられるようになっている。このシステムで,二つのタスクA,Bを実行する際,それらのタスクは共通の資源Rを排他的に使用する。それぞれのタスクA,BのCPU使用時間,資源Rの使用時間と実行順序は図に示すとおりである。二つのタスクの実行を同時に開始した場合,二つのタスクの処理が完了するまでの時間は何ミリ秒か。ここで,タスクA,Bを開始した時点では,CPU,資源Rともに空いているものとする。
| ア 120 | イ 140 | ウ 150 | エ 200 |
【解答】イ
【解説】
各タスクの進行状況を図にすると,次のようになる。
平成23年度 基本情報技術者試験 特別 午前 問18
問 CPUが1台で,入出力装置(I/O)が同時動作可能な場合の二つのタスクA,Bのスケジューリングは図のとおりであった。この二つのタスクにおいて,入出力装置がCPUと同様に,一つの要求だけを発生順に処理するように変更した場合,両方のタスクが終了するまでのCPU使用率はおよそ何%か。
| ア 43 | イ 50 | ウ 50 | エ 75 |
【解答】ウ
【解説】
各タスクの進行状況を図にすると,次のようになる。
よって,CPU使用率は,
15 ÷ 25 = 0.6(60%)
となる。
平成24年度 基本情報技術者試験 秋期 午前 問17
問 タスクスケジューリング方式の説明のうち,特定のタスクがCPU資源の割当てを待ち続ける可能性が最も高いものはどれか。
ア 各タスクの優先度を決めて,優先度が高い順に実行し,CPU割当てまでの待ち時間の長さに応じて優先度を徐々に上げていく。
イ 各タスクを実行可能待ち行列に置かれた順に実行し,一定時間が経過したら実行を中断して実行可能待ち行列の最後尾に加える。
ウ 処理予定時間が最も短いタスクから順に処理を実行する。現在実行中の処理が終了するか,又は何らかの要因によって中断されたとき,次のタスクを開始する。
エ タスクがシステムに到着した順に実行可能待ち行列の最後尾に加え,常に実行可能待ち行列の先頭のタスクにCPUを割り当てる。
【解答】ウ
【解説】
ア 動的優先順位方式
イ ラウンドロビン方式
ウ 処理時間順方式
エ 到着順方式(FCFS方式)
平成27年度 基本情報技術者試験 春期 午前 問19
問 ノンプリエンプティブなスケジューリング方式の説明として,適切なものはどれか。
ア 新しいタスクが実行可能状態になるたびに,各タスクの残りの実行時間を評価し,その時間が短いものから順に実行する。
イ 実行状態としたタスクが決められた時間内に待ち状態に遷移しないときに,そのタスクを中断して実行待ち行列にある次のタスクを実行状態とする。
ウ 実行状態としたタスクが自ら待ち状態に遷移するか終了するまで,他のタスクを実行状態とすることができない。
エ タスクが実行可能状態になったときに,そのタスクの優先度と,その時,実行状態であるタスクの優先度とを比較して,優先度が高い方のタスクを実行状態とする。
【解答】ウ
【解説】
■ 到着順方式(FCFS方式)
タスクは優先順位を持たず,到着した順に実行が終了するまでCPUを割り当てる。
※ FCFS(First Come First Served)
※ プリエンプションがないので,ノンプリエンプション方式ともいう
ア 処理時間順方式
イ ラウンドロビン方式
エ 静的優先順位方式
平成30年度 基本情報技術者試験 秋期 午前 問18
問 スケジューリングに関する記述のうち,ラウンドロビン方式の説明として,適切なものはどれか。
ア 各タスクに,均等にCPU時間を割り当てて実行させる方式である。
イ 各タスクに,ターンアラウンドタイムに比例したCPU時間を割り当てて実行させる方式である。
ウ 各タスクの実行イベント発生に応じて,リアルタイムに実行させる方式である。
エ 各タスクを,優先度の高い順に実行させる方式である。
【解答】ア
【解説】
■ ラウンドロビン方式
各タスクに,あらかじめCPUの使用時間を設定し,実行可能状態になったタスクから順に実行する。決められた時間内に処理が終わらなかった場合は,次のタスクにCPUの使用権を割り当てる(中断したタスクは,実行可能待ち行列の最後尾に移動する)。
イ 処理時間順方式
ウ イベントドリブンプリエンプション方式
エ 優先順位方式
平成28年度 基本情報技術者試験 春期 午前 問16
問 組込みリアルタイムOSで用いられる,優先度に基づくプリエンプティブなスケジューリングの利用方法として,適切なものはどれか。
ア 各タスクの実行時間を均等配分する場合に利用される。
イ 起動が早いタスクから順番に処理を行う場合に利用される。
ウ 重要度及び緊急度に応じて処理を行う場合に利用される。
エ 処理時間が短いタスクから順番に処理を行う場合に利用される。
【解答】ウ
【解説】
ア ラウンドロビン方式
イ 到着順方式(FCFS方式)
平成23年度 基本情報技術者試験 特別 午前 問22
問 組込みシステムでリアルタイムOSが用いられる理由として,適切なものはどれか。
ア アプリケーションがハングアップしても,データが失われない。
イ 期待される応答時間内にタスクや割込みを処理するための仕組みが提供される。
ウ グラフィカルなユーザインタフェースを容易に利用できる。
エ システムのセキュリティが保証される。
【解答】イ
【解説】
■ リアルタイムOS
リアルタイム処理(時間的な制約がある処理)を実行するための機能を備えたOSである。優先順位の高い処理要求が発生した場合,実行中のタスクを中断して,優先順位の高いタスクを確実に実行させる。
平成22年度 基本情報技術者試験 春期 午前 問18
問 エンジン制御,ハードディスク制御などの制御系ハードリアルタイムシステムでリアルタイムOSを活用する理由はどれか。
ア ウイルス侵入の防御のためにメモリ保護機構が必要だから。
イ 定められた時間内にイベントに対応した処理を完了させる機構が必要だから。
ウ システム全体のスループットを向上させる機構が必要だから。
エ 複数の独立したプログラムを並行して動かす機構が必要だから。
【解答】イ
【解説】
■ ハードリアルタイムシステム
遅延が許されない(遅延が発生した場合,致命的な問題が生じる)システムをいう。
例)エアバッグ制御システム,ペースメーカーなど
■ リアルタイムOS
リアルタイム処理(時間的な制約がある処理)を実行するための機能を備えたOSである。優先順位の高い処理要求が発生した場合,実行中のタスクを中断して,優先順位の高いタスクを確実に実行させる。
(令和4年度) 基本情報技術者試験 サンプル問題 科目A 問15
令和元年度 基本情報技術者試験 秋期 午前 問17
平成29年度 基本情報技術者試験 春期 午前 問17
問 図の送信タスクから受信タスクにT秒間連続してデータを送信する。1秒当たりの送信量をS,1秒当たりの受信量をRとしたとき,バッファがオーバフローしないバッファサイズLを表す関係式として適切なものはどれか。ここで,受信タスクよりも送信タスクの方が転送速度は速く,次の転送開始までの時間間隔は十分にあるものとする。
| ア L < (R - S) × T | イ L < (S - R) × T |
| ウ L ≧ (R - S) × T | エ L ≧ (S - R) × T |
【解答】エ
【解説】
バッファに溜まる最大データ量は,
(S - R) × L
である。バッファがオーバーフローしないバッファサイズLは,バッファに溜まる最大データ量以上であればよいので,
L ≧ (S - R) × T
となる。
| 【参考】 |
平成24年度 基本情報技術者試験 春期 午前 問23
平成21年度 基本情報技術者試験 秋期 午前 問18
問 様々なサイズのメモリ資源を使用するリアルタイムシステムのメモリプール管理において,可変長方式と比べた場合の固定長方式の特徴として,適切なものはどれか。
ア メモリ効率が良く,獲得及び返却の処理速度は遅く一定である。
イ メモリ効率が良く,獲得及び返却の処理速度は遅く不定である。
ウ メモリ効率が悪く,獲得及び返却の処理速度は速く一定である。
エ メモリ効率が悪く,獲得及び返却の処理速度は速く不定である。
【解答】ウ
【解説】
■ 固定区画方式
固定区画方式は,主記憶装置の記憶領域を固定長に分割してプログラムに割り当てる方式である。
図のように,複数の区画に分割するので,主記憶装置に複数のプログラムを読み込んで同時に実行することができる。また,各区画のサイズは固定長であるため管理しやすい。しかし,各区画には未使用領域が発生するので使用効率がよくないし,区画のサイズより大きいプログラムを読み込むこともできない。
■ 可変区画方式
可変区画方式は,主記憶装置の記憶領域をプログラムのサイズに合わせて割り当てる方式である。
図のように,各区画のサイズをプログラムのサイズに合わせるので,使用効率はよい。しかし,記憶領域の割り当てと解放を繰り返すと,フラグメンテーションが発生する。
平成24年度 基本情報技術者試験 秋期 午前 問18
問 OSが記憶領域の割当てと解放を繰り返すことによって,細切れの未使用領域が多数できてしまう場合がある。この現象を何というか。
| ア コンパクション | イ スワッピング |
| ウ フラグメンテーション | エ ページング |
【解答】ウ
【解説】
■ フラグメンテーション(断片化)
記憶領域の割り当てと解放を繰り返すことによってできる細切れの未使用領域が,多数できる現象をいう。
フラグメンテーションが発生すると,未使用領域の合計が十分にある場合でも,プログラムに記憶領域の割り当てができない場合がある。
平成29年度 基本情報技術者試験 秋期 午前 問19
平成27年度 基本情報技術者試験 秋期 午前 問18
問 図のメモリマップで,セグメント2が解放されたとき,セグメントを移動(動的再配置)し,分散する空き領域を集めて一つの連続領域にしたい。1回のメモリアクセスは4バイト単位で行い,読取り,書込みがそれぞれ30ナノ秒とすると,動的再配置をするために必要なメモリアクセス時間は合計何ミリ秒か。ここで,1kバイトは1,000バイトとし,動的再配置に要する時間以外のオーバヘッドは考慮しないものとする。
| ア 1.5 | イ 6.0 | ウ 7.5 | エ 12.0 |
【解答】エ
【解説】
セグメント3(800kバイト)を前方に移動させればよいので,移動回数は,
800kバイト ÷ 4バイト = 200,000(回)
となる。よって,メモリアクセス時間は,
200,000回 × 30ナノ秒(読取りにかかる時間)+ 200,000回 × 30ナノ秒(書込みにかかる時間)
= 6,000,000 + 6,000,000
= 12,000,000(ナノ秒)
=12(ミリ秒)
となる。
平成29年度 基本情報技術者試験 秋期 午前 問16
平成25年度 基本情報技術者試験 秋期 午前 問17
問 メモリリークの説明として,適切なものはどれか。
ア OSやアプリケーションのバグなどが原因で,動作中に確保した主記憶が解放されないことであり,これが発生すると主記憶中の利用可能な部分が減少する。
イ アプリケーションの同時実行数を増やした場合に,主記憶容量が不足し,処理時間のほとんどがページングに費やされ,スループットの極端な低下を招くことである。
ウ 実行時のプログラム領域の大きさに制限があるときに,必要になったモジュールを主記憶に取り込む手法である。
エ 主記憶で利用可能な空き領域の総量は足りているのに,主記憶中に不連続で散在しているので,大きなプログラムをロードする領域が確保できないことである。
【解答】ア
【解説】
■ メモリリーク
OSやアプリケーションソフトウェアのバグが原因で,確保した主記憶装置の記憶領域が解放されないことをいう。メモリリークが発生すると,プログラムに割り当て可能な記憶領域が減少する。
※ メモリリークは,ガーベジコレクション対象外の記憶領域で発生することもある
イ スラッシング
ウ オーバーレイ方式
エ フラグメンテーション
平成22年度 基本情報技術者試験 春期 午前 問20
問 仮想記憶を用いたコンピュータでのアプリケーション利用に関する記述のうち,適切なものはどれか。
ア アプリケーションには,仮想記憶を利用するためのモジュールを組み込んでおく必要がある。
イ 仮想記憶は,磁気ディスクにインストールされたアプリケーションだけが利用できる。
ウ 仮想記憶を使用していても主記憶が少ないと,アプリケーション利用時にページフォールトが多発してシステムのスループットは低下する。
エ 仮想記憶を利用するためには,個々のアプリケーションで仮想記憶を使用するという設定が必要である。
【解答】ウ
【解説】
■ 仮想記憶管理
仮想記憶(空間)とは,補助記憶装置を利用して作成した(主記憶装置よりも大きい)記憶領域のことをいう。
仮想記憶管理では,仮想記憶(空間)を作り出し,実記憶よりも大きい記憶領域を扱えるようにする。
ア,エ 仮想記憶はOSが管理する(アプリケーション側で実装や設定をする必要はない)
イ 磁気ディスクに限らず,SSDなどのフラッシュメモリでも利用可能
平成29年度 基本情報技術者試験 春期 午前 問15
平成23年度 基本情報技術者試験 特別 午前 問20
問 ページング方式の説明として,適切なものはどれか。
ア 仮想記憶空間と実記憶空間をそれぞれ固定長の領域に区切り,対応づけて管理する方式
イ 主記憶装置の異なった領域で実行できるように,プログラムを再配置する方式
ウ 主記憶装置を,同時に並行して読み書き可能な複数の領域に分ける方式
エ 補助記憶装置に,複数のレコードをまとめて読み書きする方式
【解答】ア
【解説】
■ ページング方式
ページング方式は,プログラムをページという固定長のサイズ(4kバイトなど)に分割して管理する方式である。詳細は,【参考】を参照。
イ 動的再配置
ウ メモリインタリーブ
平成26年度 基本情報技術者試験 春期 午前 問16
問 ページング方式の仮想記憶を用いることによる効果はどれか。
ア システムダウンから復旧するときに,補助記憶のページを用いることによって,主記憶の内容が再現できる。
イ 処理に必要なページを動的に主記憶に割り当てることによって,主記憶を効率的に使用できる。
ウ 頻繁に使用されるページを仮想記憶に置くことによって,アクセス速度を主記憶へのアクセスよりも速めることができる。
エ プログラムの大きさに応じて大小のページを使い分けることによって,主記憶を無駄なく使用できる。
【解答】イ
【解説】
■ ページング方式
ページング方式は,プログラムをページという固定長のサイズ(4kバイトなど)に分割して管理する方式である。詳細は,【参考】を参照。
平成29年度 基本情報技術者試験 秋期 午前 問20
問 ページング方式の仮想記憶において,ページフォールトの発生回数を増加させる要因はどれか。
ア 主記憶に存在しないページへのアクセスが増加すること
イ 主記憶に存在するページへのアクセスが増加すること
ウ 主記憶のページのうち,更新されたページの比率が高くなること
エ 長時間アクセスしなかった主記憶のページをアクセスすること
【解答】ア
【解説】
■ ページフォールト
プログラムが仮想記憶のページにアクセスした際に,そのページが主記憶装置に存在しないことにより発生する割込みのことをいう。
平成27年度 基本情報技術者試験 秋期 午前 問17
問 仮想記憶管理のページ入替え方式のうち,最後に使われてからの経過時間が最も長いページを入れ替えるものはどれか。
| ア FIFO | イ LFU | ウ LIFO | エ LRU |
【解答】エ
【解説】
■ LRU(Least Recently Used)
最後に参照されてから最も長い時間が経過したページを置き換える
ア FIFO(First In First Out)…先入れ先出しのアルゴリズム
イ LFU(Least Frequently Used)…参照回数の最も少ないページを置き換えるアルゴリズム
ウ LIFO(Last In First Out)…後入れ先出しのアルゴリズム
平成25年度 基本情報技術者試験 春期 午前 問20
問 仮想記憶管理におけるページ置換えの方式のうち,LRU制御方式はどれか。
ア 各ページに参照フラグと変更フラグを付加して管理し,参照なしかつ変更なしのページを優先して置き換える。
イ 主記憶にある全てのページを同一の確率でランダムに選択し,置き換える。
ウ 最も長い間参照されていないページを置き換える。
エ 最も長い間主記憶にあったページを置き換える。
【解答】ウ
【解説】
■ LRU(Least Recentry Used)
最後に参照してから,経過時間が最も長いページをページアウトする方式。
ア LFU(Least Frequently Used)
エ FIFO(First In First Out)
平成28年度 基本情報技術者試験 秋期 午前 問19
平成23年度 基本情報技術者試験 特別 午前 問21
問 LRUアルゴリズムで,ページ置換えの判断基準に用いられる項目はどれか。
| ア 最後に参照した時刻 | イ 最初に参照した時刻 |
| ウ 単位時間当たりの参照頻度 | エ 累積の参照回数 |
【解答】ア
【解説】
■ LRU(Least Recentry Used)
最後に参照してから,経過時間が最も長いページをページアウトする方式。
平成24年度 基本情報技術者試験 春期 午前 問22
問 ページ置換えアルゴリズムにおけるLRU方式の説明として,適切なものはどれか。
ア 最後に参照されたページを置き換える方式
イ 最後に参照されてからの経過時間が最も長いページを置き換える方式
ウ 最も参照回数の少ないページを置き換える方式
エ 最も古くから存在するページを置き換える方式
【解答】イ
【解説】
■ LRU(Least Recentry Used)
最後に参照してから,経過時間が最も長いページをページアウトする方式。
ア LIFO(Last In First Out)
ウ LFU(Least Frequently Used)
エ FIFO(First In First Out)
平成29年度 基本情報技術者試験 春期 午前 問19
問 仮想記憶方式のコンピュータにおいて,実記憶に割り当てられるページ数は3とし,追い出すページを選ぶアルゴリズムは,FIFOとLRUの二つを考える。あるタスクのページのアクセス順序が
1,3,2,1,4,5,2,3,4,5
のとき,ページを置き換える回数の組合せとして,適切なものはどれか。
| FIFO | LRU | |
| ア | 3 | 2 |
| イ | 3 | 6 |
| ウ | 4 | 3 |
| エ | 5 | 4 |
【解答】イ
【解説】
FIFOの場合は,
となり,ページを置き換える回数は,
3回
となる。LRUの場合は,
となり,ページを置き換える回数は,
6回
となる。
平成27年度 基本情報技術者試験 春期 午前 問20
平成24年度 基本情報技術者試験 秋期 午前 問19
問 ページング方式の仮想記憶において,ページ置換えアルゴリズムにLRU方式を採用する。主記憶に割り当てられるページ枠が4のとき,ページ1,2,3,4,5,2,1,3,2,6の順にアクセスすると,ページ6をアクセスする時点で置き換えられるページはどれか。ここで,初期状態では主記憶のどのページも存在しないものとする。
| ア 1 | イ 2 | ウ 4 | エ 5 |
【解答】エ
【解説】
ページ置換えアルゴリズムがLRU方式で,主記憶に割り当てられるページ枠が4なので,
となり,ページ6をアクセスする時点で置き換えられるページは,
ページ5
となる。
平成22年度 基本情報技術者試験 秋期 午前 問21
問 仮想記憶方式では,割り当てられる実記憶の容量が小さいとページアウト,ページインが頻発し,処理能力が急速に低下することがある。このような現象を何というか。
| ア スラッシング | イ スワッピング |
| ウ フラグメンテーション | エ メモリリーク |
【解答】ア
【解説】
■ スラッシング
主記憶装置の容量不足によりページフォールトが頻発し,CPU処理時間のほとんどがページング(ページインとページアウト)に費やされてアプリケーションの実行ができなくなり,CPU使用率が極端に減少するこという。
平成28年度 基本情報技術者試験 秋期 午前 問17
平成24年度 基本情報技術者試験 春期 午前 問21
問 仮想記憶システムにおいて主記憶の容量が十分でない場合,プログラムの多重度を増加させるとシステムのオーバヘッドが増加し,アプリケーションのプロセッサ使用率が減少する状態を表すものはどれか。
| ア スラッシング | イ フラグメンテーション |
| ウ ページング | エ ボトルネック |
【解答】ア
【解説】
■ スラッシング
主記憶装置の容量不足によりページフォールトが頻発し,CPU処理時間のほとんどがページング(ページインとページアウト)に費やされてアプリケーションの実行ができなくなり,CPU使用率が極端に減少するこという。
■ ボトルネック
処理性能などの向上を妨げる要素のこと
平成27年度 基本情報技術者試験 春期 午前 問18
問 仮想記憶方式のコンピュータシステムにおいて,処理の多重度を増やしたところ,ページイン,ページアウトが多発して,システムの応答速度が急激に遅くなった。このような現象を何というか。
| ア オーバレイ | イ スラッシング |
| ウ メモリコンパクション | エ ロールアウト |
【解答】イ
【解説】
■ スラッシング
主記憶装置の容量不足によりページフォールトが頻発し,CPU処理時間のほとんどがページング(ページインとページアウト)に費やされてアプリケーションの実行ができなくなり,CPU使用率が極端に減少するこという。
平成25年度 基本情報技術者試験 春期 午前 問19
問 主記憶の管理方式とマルチプログラミングでのプログラムの多重度の組合せで,スラッシングが発生しやすいのはどれか。
| 主記憶の管理方式 | プログラムの多重度 | |
| ア | 仮想記憶方式 | 大きい |
| イ | 仮想記憶方式 | 小さい |
| ウ | 実記憶方式 | 大きい |
| エ | 実記憶方式 | 小さい |
【解答】ア
【解説】
■ スラッシング
主記憶装置の容量不足によりページフォールトが頻発し,CPU処理時間のほとんどがページング(ページインとページアウト)に費やされてアプリケーションの実行ができなくなり,CPU使用率が極端に減少するこという。
平成24年度 基本情報技術者試験 春期 午前 問24
問 シェルのリダイレクト機能による実現の可否に関する記述のうち,適切なものはどれか。
ア 標準出力をファイルに切り替えることはできないが,標準入力をファイルに切り替えることはできる。
イ 標準出力をファイルに追加することはできないが,標準入力と標準出力をファイルに切り替えることはできる。
ウ 標準入力と標準出力をファイルに切り替えることができ,標準出力をファイルに追加することもできる。
エ 標準入力をファイルに切り替えることはできないが,標準出力をファイルに切り替えることはできる。
【解答】ウ
【解説】
■ シェル
シェルとは,利用者からの操作の受け付けや,情報の表示などを行うソフトウェアのことをいう。受け付けた操作に対応する動作を,カーネルに指示したりする。
※ シェルはOSを構成するソフトウェアのひとつで,UNIXやWindowsのコマンドプロンプトなどがある。キーボード(標準入力)からコマンドを入力し,結果をディスプレイ(標準出力)に出力する。
● リダイレクト
リダイレクトは,標準入力や標準出力を変更する機能のことをいう。
※ 入力や出力をファイルに変更することができる(出力しないという設定も可能)
平成29年度 基本情報技術者試験 秋期 午前 問17
問 ソフトウェア制御における,ポーリング制御はどれか。
ア CPUが状態レジスタ又はビジー信号などを読み出して,入出力装置の状態を監視する。
イ 実行中の処理を一時的に中断して,緊急度の高い別の処理を実行する。
ウ 送信側のタスクがメモリにデータを格納し,受信側のタスクにそのアドレスを伝える。
エ 複数のタスクが利用する共有資源を,一つのタスクが占有できるようにする。
【解答】ア
【解説】
■ ポーリング制御
各装置の情報を一定時間ごとに収集し,その情報を基にソフトウェアを円滑に処理させる制御方式である。
※ イベントを監視するのが目的
イ 割込み
エ 排他制御
| 【参考】 |
平成31年度 基本情報技術者試験 春期 午前 問17
問 デバイスドライバの説明として,適切なものはどれか。
ア PCに接続された周辺機器を制御するソフトウェア
イ アプリケーションプログラムをPCに導入するソフトウェア
ウ キーボードなどの操作手順を登録して,その操作を自動化するソフトウェア
エ 他のPCに入り込んで不利益をもたらすソフトウェア
【解答】ア
【解説】
■ デバイスドライバ
ハードウェア(周辺機器)を制御・管理するためのソフトウェアである。各機器に依存した処理を行うので,機器ごとに必要になる。
イ インストーラ
エ マルウェア
平成27年度 基本情報技術者試験 秋期 午前 問11
問 デバイスドライバの役割として,適切なものはどれか。
ア アプリケーションプログラムの要求に従って,ハードウェアを直接制御する。
イ 実行を待っているタスクの中から,次に実行するタスクを決定する。
ウ 複数のウィンドウの,画面上での表示状態を管理する。
エ 利用者が入力するコマンド文字列を解釈して,対応するプログラムを起動する。
【解答】ア
【解説】
■ デバイスドライバ
ハードウェア(周辺機器)を制御・管理するためのソフトウェアである。各機器に依存した処理を行うので,機器ごとに必要になる。
イ タスクスケジューラー
ウ ウィンドウマネージャー
エ シェル
平成28年度 基本情報技術者試験 春期 午前 問17
問 入出力管理におけるバッファの機能として,適切なものはどれか。
ア 入出力装置が利用可能になったことを,入出力装置が処理装置に伝える。
イ 入出力装置と処理装置との間に特別な記憶域を設け,処理速度の違いを緩和する。
ウ 入出力装置と処理装置との間のデータ交換に階層を設けることによって,入出力装置固有の仕様を意識せずに利用できる。
エ 入出力装置をファイルと同じように取り扱えるようにする。
【解答】イ
【解説】
■ バッファ
CPUと周辺機器の間でデータのやり取りが発生した場合に,そのデータを一時的に格納するためのメモリ領域のことをいう。
※ CPUと周辺機器では速度差が大きく,入出力命令を出した際にスループットが低下してしまう ⇒ バッファを利用すると,CPUは入出力処理の終了を待たずに,次の処理を行うことができる ⇒ スループットが大幅に向上する
イ 割込み
| 【参考】 |
平成26年度 基本情報技術者試験 春期 午前 問17
問 データ管理ユーティリティの一つである,アーカイバの機能を説明したものはどれか。
ア 磁気ディスクに,データを記録するための領域と,それを管理するための領域を作成する。
イ データのバックアップや配布のために,複数のファイルを一つにまとめたり,元に戻したりする。
ウ 不正使用や破壊からデータを守るファイルプロテクトや,不正コピー防止のためのコピープロテクトなどによって,データを保護する。
エ フラグメンテーションが発生した磁気ディスクで,ファイルを可能な限り連続した領域に再配置する。
【解答】イ
【解説】
■ アーカイブファイル
関連する複数のファイルを1つにまとめたファイル
※ アーカイバ…複数のファイルを1つにまとめるソフトウェア。圧縮機能を持つものが多い
平成25年度 基本情報技術者試験 秋期 午前 問19
問 直接編成ファイルにおけるレコードのキー値を格納アドレスに変換したハッシュ値の分布として,理想的なものはどれか。
| ア 一様分布 | イ 幾何分布 | ウ 二項分布 | エ ポアソン分布 |
【解答】ア
【解説】
■ 一様分布
すべての事象の発生確率が等しい分布。
※ ハッシュ値に偏りがない場合は一様分布で近似される
平成28年度 基本情報技術者試験 秋期 午前 問20
問 格納アドレスが1~6の範囲の直接編成ファイルにおいて,次の条件でデータを格納した場合,アドレス1に格納されているデータのキー値はどれか。
〔条件〕
(1) キー値が3,4,8,13,14,18の順でデータを格納する。
(2) データのキー値を5で割った余りに1を加えた値を格納アドレスにする。
(3) 格納アドレスに既にデータがある場合には,次のアドレスに格納する。これを格納できるまで繰り返す。最終アドレスの次は先頭とする。
(4) 初期状態では,ファイルは何も格納されていない。
| ア 8 | イ 13 | ウ 14 | エ 18 |
【解答】イ
【解説】
条件に従いデータを格納すると,
となる。よって,アドレス1に格納されているデータのキー値は,
13
となる。
(令和4年度) 基本情報技術者試験 サンプル問題 科目A 問17
問 三つの媒体A~Cに次の条件でファイル領域を割り当てた場合,割り当てた領域の総量が大きい順に媒体を並べたものはどれか。
〔条件〕
(1) ファイル領域を割り当てる際の媒体選択アルゴリズムとして,空き領域が最大の媒体を選択する方式を採用する。
(2) 割当て要求されるファイル領域の大きさは,順に90,30,40,40,70,30(Mバイト)であり,割り当てられたファイル領域は,途中で解放されない。
(3) 各媒体は容量が同一であり,割当て要求に対して十分な大きさをもち,初めは全て空きの状態である。
(4) 空き領域の大きさが等しい場合には,A,B,Cの順に選択する。
| ア A,B,C | イ A,C,B | ウ B,A,C | エ C,B,A |
【解答】エ
【解説】
条件に従いファイル領域を与えると,次のようになる。
(令和4年度) 基本情報技術者試験 サンプル問題 科目A 問18
平成30年度 基本情報技術者試験 春期 午前 問17
平成26年度 基本情報技術者試験 秋期 午前 問19
問 ファイルシステムの絶対パス名を説明したものはどれか。
ア あるディレクトリから対象ファイルに至る幾つかのパス名のうち,最短のパス名
イ カレントディレクトリから対象ファイルに至るパス名
ウ ホームディレクトリから対象ファイルに至るパス名
エ ルートディレクトリから対象ファイルに至るパス名
【解答】エ
【解説】
■ パス指定
ファイルやディレクトリーまでの経路のことをいう。
| 絶対パス指定 | ルートディレクトリーから目的のファイルまでを指定する記述方式 |
| 相対パス指定 | カレントディレクトリーから目的のファイルまでを指定する記述方式 |
※ カレントディレクトリー…現時点で作業を行っているディレクトリーのこと
また,パスを指定する場合,次のような記号を使用する。
| \ | ディレクトリーの区切りを表す |
| . | カレントディレクトリーを表す |
| .. | 1つ上の階層のディレクトリーを表す |
● 具体的
平成21年度 基本情報技術者試験 春期 午前 問21
問 絶対パス名 \a\a\b\c をもつディレクトリがカレントディレクトリであるとき,相対パス名 .\..\..\a\b\file をもつファイルを,絶対パス名で表現したものはどれか。ここで,ディレクトリ及びファイルの指定方法は,次の規則に従うものとする。
〔ディレクトリ及びファイルの指定方法〕
(1) ファイルは,“ディレクトリ名\…\ディレクトリ名\ファイル名” のように,経路上のディレクトリを順に “\” で区切って並べた後に,“\” とファイル名を指定する。
(2) カレントディレクトリは “.” で表す。
(3) 1階層上のディレクトリは “..” で表す。
(4) 始まりが “\” のときは,左端にルートディレクトリが省略されているものとする。
(5) 始まりが “\”,“.”,“..” のいずれでもないときは,左端にカレントディレクトリ配下であることを示す “.\” が省略されているものとする。
| ア \a\b\file | イ \a\a\b\file |
| ウ \a\a\a\b\file | エ \a\a\b\a\b\file |
【解答】ウ
【解説】
目的のファイルの場所は,
である。よって,この位置を絶対パス名で表現すると,
\a\a\a\b\file
となる。
平成29年度 基本情報技術者試験 春期 午前 問18
問 A,Bという名の複数のディレクトリが,図に示す構造で管理されている。“\B\A\B” がカレントディレクトリになるのは,カレントディレクトリをどのように移動した場合か。ここで,ディレクトリの指定は次の方法によるものとし,→ は移動の順序を示す。
〔ディレクトリの指定方法〕
(1) ディレクトリは,“ディレクトリ名\…\ディレクトリ名” のように,経路上のディレクトリを順に “\” で区切って並べた後に,“\” とディレクトリ名を指定する。
(2) カレントディレクトリは,“.” で表す。
(3) 1階層上のディレクトリは,“..” で表す。
(4) 始まりが “\” のときは,左端にルートディレクトリが省略されているものとする。
(5) 始まりが “\”,“.”,“..” のいずれでもないときは,左端に “.\” が省略されているものとする。
| ア \A → ..\B → .\A\B | イ \B → .\B\A → ..\B |
| ウ \B → \A → \B | エ \B\A → ..\B |
【解答】ア
【解説】
目的のディレクトリーは,
である。各選択肢の移動を,それぞれたどると,次のようになる。
平成21年度 基本情報技術者試験 秋期 午前 問19
問 A,Bというディレクトリ名をもつ複数個のディレクトリが図の構造で管理されている。
カレントディレクトリを \A\B → .. → ..\B → .\A の順に移動させた場合,最終的なカレントディレクトリはどこか。ここで,ディレクトリの指定方法は次のとおりとする。
〔ディレクトリの指定方法〕
(1) ディレクトリは,“ディレクトリ名\…\ディレクトリ名” のように,経路上のディレクトリを順に “\” で区切って並べた後に “\” とディレクトリ名を指定する。
(2) カレントディレクトリは “.” で表す。
(3) 1階層上のディレクトリは “..” で表す。
(4) 始まりが “\” のときは,左端にルートディレクトリが省略されているものとする。
(5) 始まりが “\”,“.”,“..” のいずれでもないときは,左端にカレントディレクトリ配下であることを表す “.\” が省略されているものとする。
| ア \A | イ \A\A | ウ \A\B\A | エ \B\A |
【解答】エ
【解説】
目的のディレクトリーは,
である。各選択肢の移動を,それぞれたどると,次のようになる。
平成30年度 基本情報技術者試験 春期 午前 問57
問 サーバに接続されたディスクのデータのバックアップに関する記述のうち,最も適切なものはどれか。
ア 一定の期間を過ぎて利用頻度が低くなったデータは,現在のディスクから消去するとともに,バックアップしておいたデータも消去する。
イ システムの本稼働開始日に全てのデータをバックアップし,それ以降は作業時間を短縮するために,更新頻度が高いデータだけをバックアップする。
ウ 重要データは,バックアップの媒体を取り違えないように,同一の媒体に上書きでバックアップする。
エ 複数のファイルに分散して格納されているデータは,それぞれのファイルへの一連の更新処理が終了した時点でバックアップする。
【解答】エ
【解説】
■ バックアップファイル
重要なファイルを複製したファイル。ファイルの破損に備えて,定期的に複製し退避する。
ア バックアップしておいたデータは消去しない
イ 更新頻度が低いデータはバックアップされないので,消失する恐れがある
ウ 機器の故障によるデータの消失を避けるため,別の媒体にバックアップする
平成29年度 基本情報技術者試験 秋期 午前 問56
(類似) 平成25年度 基本情報技術者試験 秋期 午前 問57
(類似) 平成23年度 基本情報技術者試験 特別 午前 問55
問 新規システムにおけるデータのバックアップ方法に関する記述のうち,最も適切なものはどれか。
ア 業務処理がバックアップ処理と重なると応答時間が長くなる可能性がある場合には,両方の処理が重ならないようにスケジュールを立てる。
イ バックアップ処理時間を短くするためには,バックアップデータをバックアップ元データと同一の記憶媒体内に置く。
ウ バックアップデータからの復旧時間を短くするためには,差分バックアップを採用する。
エ バックアップデータを長期間保存するためには,ランダムアクセスが可能な媒体を使用する。
【解答】ア
【解説】
■ バックアップファイル
重要なファイルを複製したファイル。ファイルの破損に備えて,定期的に複製し退避する。
イ 機器の故障によるデータの消失を避けるため,別の媒体にバックアップする
ウ 復旧時間の長さは,フルバックアップからの復旧の方が短い
エ 保存期間は,ランダムアクセスが可能な媒体より磁気テープの方が長い
令和元年度 基本情報技術者試験 秋期 午前 問19
問 バックアップ方式の説明のうち,増分バックアップはどれか。ここで,最初のバックアップでは,全てのファイルのバックアップを取得し,OSが管理しているファイル更新を示す情報はリセットされるものとする。
ア 最初のバックアップの後,ファイル更新を示す情報があるファイルだけをバックアップし,ファイル更新を示す情報は変更しないでそのまま残しておく。
イ 最初のバックアップの後,ファイル更新を示す情報にかかわらず,全てのファイルをバックアップし,ファイル更新を示す情報はリセットする。
ウ 直前に行ったバックアップの後,ファイル更新を示す情報があるファイルだけをバックアップし,ファイル更新を示す情報はリセットする。
エ 直前に行ったバックアップの後,ファイル更新を示す情報にかかわらず,全てのファイルをバックアップし,ファイル更新を示す情報は変更しないでそのまま残しておく。
【解答】ウ
【解説】
■ 増分バックアップ
直前のバックアップから追加・変更されたデータを複製し退避する。
- バックアップにかかる時間が短い
- バックアップのデータ量を少なくできる
- リストア(復元)に手間がかかる
ア 差分バックアップ
イ,エ フルバックアップ
平成24年度 基本情報技術者試験 秋期 午前 問54
問 データの追加・変更・削除が,少ないながらも一定の頻度で行われるデータベースがある。このデータベースのフルバックアップを磁気テープに取得する時間間隔を今までの2倍にした。このとき,データベースのバックアップ又は復旧に関する記述のうち,適切なものはどれか。
ア ジャーナル情報によって復旧するときの処理時間が平均して約2倍になる。
イ フルバックアップ1回当たりの磁気テープ使用量が約2倍になる。
ウ フルバックアップ1回当たりの磁気テープ使用量が約半分になる。
エ フルバックアップ取得の平均実行時間が約2倍になる。
【解答】ア
【解説】
フルバックアップを磁気テープに取得する時間間隔を2倍にすると,ジャーナル(ログ)情報も平均して約2倍になる。よって,復旧時間も約2倍になる。
イ,ウ,エ フルバックアップのデータ量は,毎回,大きく増えることはない。
平成25年度 基本情報技術者試験 春期 午前 問21
問 次の仕様のバックアップシステムにおいて,金曜日に変更されたデータの増分バックアップを取得した直後に磁気ディスクが故障した。修理が完了した後,データを復元するのに必要となる時間は何秒か。ここで,増分バックアップは直前に行ったバックアップとの差分だけをバックアップする方式であり,金曜日に変更されたデータの増分バックアップを取得した磁気テープは取り付けられた状態であって,リストア時には磁気テープを1本ごとに取り替える必要がある。また,次の仕様に示された以外の時間は無視する。
| ア 1,250 | イ 1,450 | ウ 1,750 | エ 1,850 |
【解答】エ
【解説】
まず,日曜日にフルバックアップしたデータを復元する。日曜日の内容の復元にかかる時間は,
磁気テープの取替え時間 + リストア時間
= 100秒 + 100Gバイト × 10秒/Gバイト
= 100 + 1,000
= 1,100秒
である。次に,月~金曜日に増分バックアップしたデータを復元する。月~金曜日の内容の復元にかかる時間は,
(磁気テープの取替え時間 + リストア時間)× 5日(月~金曜日)
=(100秒 + 5Gバイト × 10秒/Gバイト) × 5日
=(100 + 50)× 5
= 150 × 5
= 750秒
である。よって,すべてのデータを復元するのにかかる時間は,
1,100秒 + 750秒 = 1,850秒
となる。
平成28年度 基本情報技術者試験 春期 午前 問18
問 UNIXにおいて,あるコマンドの標準出力を,直接別のコマンドの標準入力につなげる機能はどれか。
| ア パイプ | イ バックグラウンドジョブ |
| ウ ブレース展開 | エ リダイレクト |
【解答】ア
【解説】
■ パイプ
あるプログラムの出力を,別のプログラムの入力として渡す仕組みをいう。UNIX系のOSなどでプログラムを実行する際に,「|」(パイプ;縦棒)の後ろに別のプログラムを指定する。
| 【参考】 |
平成22年度 基本情報技術者試験 春期 午前 問21
問 UNIXの階層的ファイルシステムにおいて,アカウントをもつ一般の利用者がファイルの保存などに使う階層で最上位のものはどれか。
| ア カレントディレクトリ | イ デスクトップディレクトリ |
| ウ ホームディレクトリ | エ ルートディレクトリ |
【解答】ウ
【解説】
■ ホームディレクトリー
アカウントを持つ利用者がログインした時点で位置づけられるディレクトリーをいう。利用者は,ホームディレクトリーの下で,ディレクトリーやファイルを管理することができる。
まとめ
今回は,基本情報技術者試験の過去問題・サンプル問題・公開問題のうち,ソフトウェア(オペレーティングシステム)分野に関するものを集め,シンプルにまとめてみました。みなさんは,どのくらい解けましたか?はじめは難しく感じるかもしれませんが,繰り返し問題を解くことで,少しずつ理解できるようになると思います。8割以上(できれば9割以上)解けるようになることを目標に,ぜひ取り組んでみてください。また,一度解けるようになっても,時間が経つと忘れてしまうことがあります。1週間後や1か月後など,期間をあけてもう一度解き直すことで,理解の定着につながると思います。