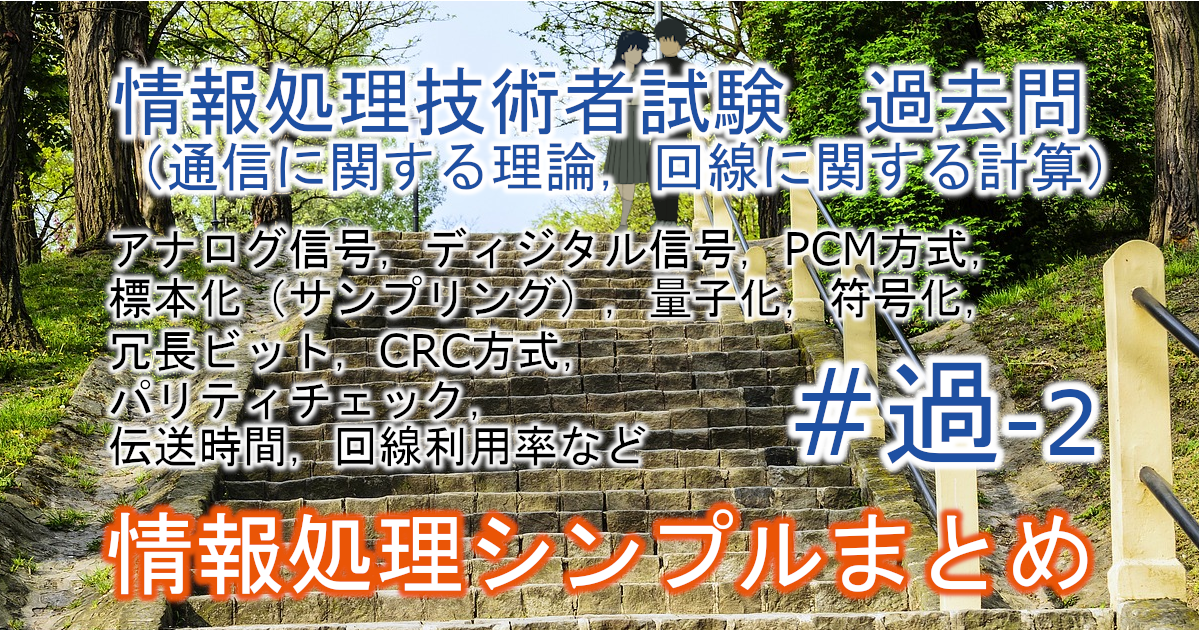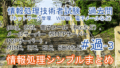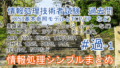情報処理技術者試験(今のところは基本情報技術者試験)の過去問(ネットワーク-通信に関する理論,回線に関する計算)を集めて,シンプルにまとめています。1秒間に送信できる文字数,D/A変換器の出力電圧の変化,アナログ信号,ディジタル信号,PCM方式,標本化(サンプリング),量子化,符号化,冗長ビット,CRC方式,パリティチェック(垂直パリティ),伝送時間,伝送遅延時間,応答時間,再生開始前のバッファリング時間,回線利用率について,理解度を確認することができます。解けなかった問題や,完全に理解できていない問題については,【参考】にあるリンク先ページを読んで,もう一度,解いてみてください。難しい問題もあると思いますが,繰り返し解くことにより,だんだんと身に付いてきますので,根気よく頑張りましょう。
- 平成25年度 基本情報技術者試験 春期 午前 問2
- 平成28年度 基本情報技術者試験 秋期 午前 問5
- 平成29年度 基本情報技術者試験 春期 午前 問20
- 平成25年度 基本情報技術者試験 秋期 午前 問22
- 平成23年度 基本情報技術者試験 特別 午前 問14
- 平成28年度 基本情報技術者試験 春期 午前 問4
- 平成25年度 基本情報技術者試験 秋期 午前 問4
- 平成25年度 基本情報技術者試験 春期 午前 問3
- 平成30年度 基本情報技術者試験 秋期 午前 問11
- 平成27年度 基本情報技術者試験 春期 午前 問10
- 平成29年度 基本情報技術者試験 秋期 午前 問2
- 平成22年度 基本情報技術者試験 秋期 午前 問4
- 平成26年度 基本情報技術者試験 春期 午前 問11
- 平成25年度 基本情報技術者試験 春期 午前 問4
- 平成28年度 基本情報技術者試験 秋期 午前 問35
- 平成28年度 基本情報技術者試験 春期 午前 問31
- 平成25年度 基本情報技術者試験 秋期 午前 問33
- 平成30年度 基本情報技術者試験 春期 午前 問31
- 平成27年度 基本情報技術者試験 春期 午前 問31
- 平成24年度 基本情報技術者試験 春期 午前 問34
- (令和4年度) 基本情報技術者試験 サンプル問題 科目A 問26
- 平成30年度 基本情報技術者試験 秋期 午前 問31
- 平成27年度 基本情報技術者試験 秋期 午前 問30
- 平成21年度 基本情報技術者試験 春期 午前 問36
- 平成22年度 基本情報技術者試験 春期 午前 問34
- 平成29年度 基本情報技術者試験 秋期 午前 問31
- 平成26年度 基本情報技術者試験 秋期 午前 問31
- 令和元年度 基本情報技術者試験 秋期 午前 問30
- 平成24年度 基本情報技術者試験 秋期 午前 問32
- 平成29年度 基本情報技術者試験 春期 午前 問30
- 平成25年度 基本情報技術者試験 春期 午前 問32
- まとめ
平成25年度 基本情報技術者試験 春期 午前 問2
問 1秒間に一定間隔で16個のパルスを送ることができる通信路を使って,0~9,A~Fの16種類の文字を送るとき,1秒間に最大何文字を送ることができるか。ここで,1ビットは1個のパルスで表し,圧縮は行わないものとする。
| ア 1 | イ 2 | ウ 4 | エ 8 |
【解答】ウ
【解説】
0~9,A~Fの16文字を識別するためには,
のように,4ビット必要である。よって,1秒間に16個のパルスを送ることができる通信路では1秒間に最大で,
16ビット ÷ 4ビット = 4文字
を送ることができる。
| 【参考】 |
平成28年度 基本情報技術者試験 秋期 午前 問5
問 標本化,符号化,量子化の三つの工程で,アナログをディジタルに変換する場合の順番として,適切なものはどれか。
| ア 標本化,量子化,符号化 | イ 符号化,量子化,標本化 |
| ウ 量子化,標本化,符号化 | エ 量子化,符号化,標本化 |
【解答】ア
【解説】
たとえば,音声情報などのアナログ信号をディジタル信号に変換する方式であるPCMの場合は,標本化(サンプリング)⇒量子化⇒符号化の順となる。
平成29年度 基本情報技術者試験 春期 午前 問20
平成25年度 基本情報技術者試験 秋期 午前 問22
問 分解能が8ビットのD/A変換器に,ディジタル値0を入力したときの出力電圧が0Vとなり,ディジタル値128を入力したときの出力電圧が2.5Vとなる場合,最下位の1ビットの変化による当該D/A変換器の出力電圧の変化は何Vか。
| ア 2.5/128 | イ 2.5/255 | ウ 2.5/256 | エ 2.5/512 |
【解答】ア
【解説】
最下位の1ビットの変化による出力電圧の変化は,2.5Vを128等分した値になるので,
2.5/128
となる。
| 【参考】 |
平成23年度 基本情報技術者試験 特別 午前 問14
問 アナログ音声信号を,サンプリング周波数44.1kHzのPCM方式でディジタル録音するとき,録音されるデータ量は何によって決まるか。
| ア 音声信号の最高周波数 | イ 音声信号の最大振幅 |
| ウ 音声データの再生周波数 | エ 音声データの量子化ビット数 |
【解答】エ
【解説】
■ PCM
音声情報などのアナログ信号をディジタル信号に変換する方式である。音声データのデータ量は,サンプリング周波数と量子化ビット数で決まる。
平成28年度 基本情報技術者試験 春期 午前 問4
平成25年度 基本情報技術者試験 秋期 午前 問4
平成25年度 基本情報技術者試験 春期 午前 問3
問 PCM方式によって音声をサンプリング(標本化)して8ビットのディジタルデータに変換し,圧縮せずにリアルタイムで転送したところ,転送速度は64,000ビット/秒であった。このときのサンプリング間隔は何マイクロ秒か。
| ア 15.6 | イ 46.8 | ウ 125 | エ 128 |
【解答】ウ
【解説】
1秒間に行われるサンプリングの回数は,
64,000ビット/秒 ÷ 8ビット = 8,000回
である。よって,サンプリング間隔は,
1秒 ÷ 8,000回 = 0.000125秒 = 125μ秒
である。
平成30年度 基本情報技術者試験 秋期 午前 問11
平成27年度 基本情報技術者試験 春期 午前 問10
問 メモリのエラー検出及び訂正にECCを利用している。データバス幅2nビットに対して冗長ビットがn+2ビット必要なとき,128ビットのデータバス幅に必要な冗長ビットは何ビットか。
| ア 7 | イ 8 | ウ 9 | エ 10 |
【解答】ウ
【解説】
128 = 27 なので,128ビットのデータバス幅に必要な冗長ビットは,
7 + 2 = 9ビット
となる。
| 【参考】 |
平成29年度 基本情報技術者試験 秋期 午前 問2
平成22年度 基本情報技術者試験 秋期 午前 問4
問 送信側では,ビット列をある生成多項式で割った余りをそのビット列に付加して送信し,受信側では,受信したビット列が同じ生成多項式で割り切れるか否かで誤りの発生を判断する誤り検査方式はどれか。
| ア CRC方式 | イ 垂直パリティチェック方式 |
| ウ 水平パリティチェック方式 | エ ハミング符号方式 |
【解答】ア
【解説】
■ CRC(Cyclic Redundancy Check)方式(巡回冗長検査)
バースト誤り(連続した誤り)を検出できる。送信側では送信データにCRC符号(送信データ(ビット列)を適当な生成多項式で割った余り)を付加し,受信側では受信したビット列を同じ(送信時に使用した)生成多項式で割り,割り切れるか否かで,誤りの有無を判断する。
※ 誤りを検出するのみで,訂正はできない
平成26年度 基本情報技術者試験 春期 午前 問11
問 メモリモジュールのパリティチェックの目的として,適切なものはどれか。
ア メモリモジュールに電源が供給されているかどうかを判定する。
イ 読出し時に,エラーが発生したかどうかを検出する。
ウ 読出し時に,エラーを検出して自動的に訂正する。
エ 読み出したデータを暗号化する。
【解答】イ
【解説】
■ パリティチェック方式
送信データにパリティビットを付加することで誤りを検出できる。
※ 誤りを検出するのみで,訂正はできない
平成25年度 基本情報技術者試験 春期 午前 問4
問 通信回線の伝送誤りに対処するパリティチェック方式(垂直パリティ)の記述として,適切なものはどれか。
ア 1ビットの誤りを検出できる。
イ 1ビットの誤りを訂正でき,2ビットの誤りを検出できる。
ウ 奇数パリティならば1ビットの誤りを検出できるが,偶数パリティでは1ビットの誤りも検出できない。
エ 奇数パリティならば奇数個のビット誤りを,偶数パリティならば偶数個のビット誤りを検出できる。
【解答】ア
【解説】
■ パリティチェック方式
送信データにパリティビットを付加することで誤りを検出できる。
※ 誤りを検出するのみで,訂正はできない
■ 垂直パリティと水平パリティ
垂直パリティの場合は,送信データそれぞれに対してパリティビットを付加する。水平パリティの場合は,各データブロックのそれぞれに対してパリティビットを付加する。
イ 垂直・水平パリティ
平成28年度 基本情報技術者試験 秋期 午前 問35
問 地上から高度約36,000kmの静止軌道衛星を中継して,地上のA地点とB地点で通信をする。衛星とA地点,衛星とB地点の距離がどちらも37,500kmであり,衛星での中継による遅延を10ミリ秒とするとき,Aから送信し始めたデータがBに到達するまでの伝送遅延時間は何秒か。ここで,電波の伝搬速度は3×108m/秒とする。
| ア 0.13 | イ 0.26 | ウ 0.35 | エ 0.52 |
【解答】イ
【解説】
伝送遅延時間は,
(37,500km × 2)3 × 108 m/秒 + 10ミリ秒
= 0.25秒 + 0.01秒
= 0.26秒
となる。
| 【参考】 |
平成28年度 基本情報技術者試験 春期 午前 問31
平成25年度 基本情報技術者試験 秋期 午前 問33
問 64kビット/秒の回線を用いて106バイトのファイルを送信するとき,伝送におよそ何秒掛かるか。ここで,回線の伝送効率は80%とする。
| ア 19.6 | イ 100 | ウ 125 | エ 156 |
【解答】エ
【解説】
伝送時間は,
データ量実効速度 = データ量(回線速度 × 伝送効率)
= 106バイト × 8ビット64kビット/秒 × 0.8
= 156.25秒(約156秒)
となる。
平成30年度 基本情報技術者試験 春期 午前 問31
平成27年度 基本情報技術者試験 春期 午前 問31
平成24年度 基本情報技術者試験 春期 午前 問34
問 10Mバイトのデータを100,000ビット/秒の回線を使って転送するとき,転送時間は何秒か。ここで,回線の伝送効率を50%とし,1Mバイト=106バイトとする。
| ア 200 | イ 400 | ウ 800 | エ 1,600 |
【解答】エ
【解説】
伝送時間は,
データ量実効速度 = データ量(回線速度 × 伝送効率)
= 10Mバイト × 8ビット100,000ビット × 0.5
= 1,600秒
となる。
(令和4年度) 基本情報技術者試験 サンプル問題 科目A 問26
平成30年度 基本情報技術者試験 秋期 午前 問31
平成27年度 基本情報技術者試験 秋期 午前 問30
平成21年度 基本情報技術者試験 春期 午前 問36
問 1.5Mビット/秒の伝送路を用いて12Mバイトのデータを転送するのに必要な伝送時間は何秒か。ここで,伝送路の伝送効率を50%とする。
| ア 16 | イ 32 | ウ 64 | エ 128 |
【解答】エ
【解説】
伝送時間は,
データ量実効速度 = データ量(回線速度 × 伝送効率)
= 12Mバイト × 8ビット1.5Mビット × 0.5
= 128秒
となる。
平成22年度 基本情報技術者試験 春期 午前 問34
問 設置場所の異なるクライアントとサーバ間で,次の条件で通信を行う場合の応答時間は何秒か。ここで,クライアントの送信処理の始まりから受信処理が終了するまでを応答時間とし,距離による遅延は考慮しないものとする。
| ア 1.4 | イ 3.8 | ウ 5.0 | エ 5.8 |
【解答】エ
【解説】
応答時間は,
伝送時間(上下)+ クライアントの処理時間 + サーバの処理時間
= (1Mバイト + 2Mバイト)× 8ビット8Mビット × 0.6 + 0.4秒 + 0.4秒
= 5秒 + 0.4秒 + 0.4秒
= 5.8秒
となる。
平成29年度 基本情報技術者試験 秋期 午前 問31
平成26年度 基本情報技術者試験 秋期 午前 問31
問 符号化速度が192kビット/秒の音声データ2.4Mバイトを,通信速度が128kビット/秒のネットワークを用いてダウンロードしながら途切れることなく再生するためには,再生開始前のデータのバッファリング時間として最低何秒間が必要か。
| ア 50 | イ 100 | ウ 150 | エ 250 |
【解答】ア
【解説】
音声データの再生時間は,
2.4Mバイト × 8ビット192kビット/秒
= 100秒
である。また,ダウンロードにかかる時間は,
2.4Mバイト × 8ビット128kビット/秒
= 150秒
である。よって,途切れることなく再生するために必要なバッファリング時間は,
150秒 - 100秒 = 50秒
となる。
令和元年度 基本情報技術者試験 秋期 午前 問30
問 10Mビット/秒の回線で接続された端末間で,平均1Mバイトのファイルを,10秒ごとに転送するときの回線利用率は何%か。ここで,ファイル転送時には,転送量の20%が制御情報として付加されるものとし,1Mビット=106ビットとする。
| ア 1.2 | イ 6.4 | ウ 8.0 | エ 9.6 |
【解答】エ
【解説】
実効速度は,
データ量(伝送時間×伝送効率)
= 1Mバイト × 8ビット × 1.210秒
= 0.96Mbps
であるので,伝送効率(回線利用率)は,
実効速度回線速度
= 0.96Mbps10Mビット/秒
= 0.096(9.6%)
となる。
平成24年度 基本情報技術者試験 秋期 午前 問32
問 通信速度64,000ビット/秒の専用線で接続された端末間で,平均1,000バイトのファイルを,2秒ごとに転送するときの回線利用率は何%か。ここで,ファイル転送に伴い,転送量の20%の制御情報が付加されるものとする。
| ア 0.9 | イ 6.3 | ウ 7.5 | エ 30.0 |
【解答】ウ
【解説】
実効速度は,
データ量(伝送時間×伝送効率)
= 1,000バイト × 8ビット × 1.22秒
= 4,800bps
であるので,伝送効率(回線利用率)は,
実効速度回線速度
= 4,800bps64,000ビット/秒
= 0.075(7.5%)
となる。
平成29年度 基本情報技術者試験 春期 午前 問30
平成25年度 基本情報技術者試験 春期 午前 問32
問 本社と工場との間を専用線で接続してデータを伝送するシステムがある。このシステムでは2,000バイト/件の伝票データを2件ずつまとめ,それに400バイトのヘッダ情報を付加して送っている。伝票データは,1時間に平均100,000件発生している。回線速度を1Mビット/秒としたとき,回線利用率はおよそ何%か。
| ア 6.1 | イ 44 | ウ 49 | エ 53 |
【解答】ウ
【解説】
伝送効率(回線利用率)は,
実効速度回線速度
= (2,000バイト × 2 + 400バイト)× 8ビット ×(100,000 ÷ 2)件1Mビット/秒 × 60秒 × 60分
≒ 0.48…(約49%)
となる。
まとめ
今回は,情報処理技術者試験の過去問(通信に関する理論,回線に関する計算)を集めて,シンプルにまとめてみました。みなさん,どのくらい解けましたか?はじめは難しく感じると思いますが,繰り返し解くことにより,少しずつ理解できるようになると思います(8割以上(できれば9割以上)解けるようになるまで頑張りましょう)。また,解けるようになっても時間が経つと忘れることもありますので,たとえば,1週間後とか,1か月後とかに,また,やってみてください。